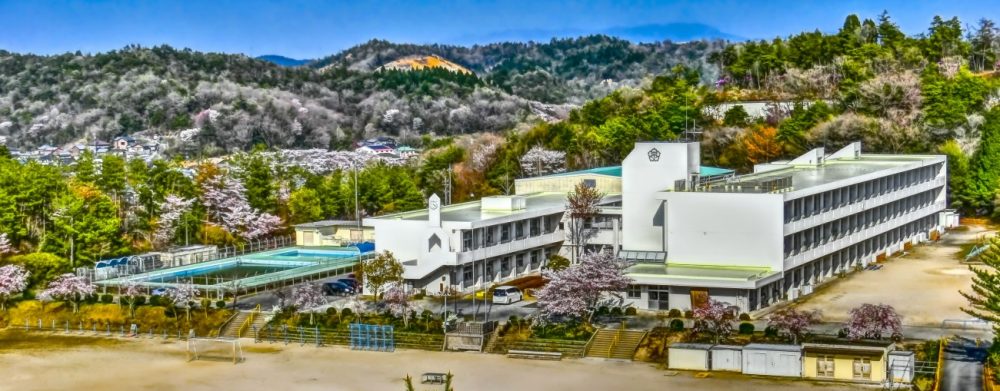卒業を迎える6年生に向けて、この日は給食が少しスペシャルなものになります。
多治見市はこのような取り組みがとても早く、かつては「バイキング給食」というような名前で行われていたと思います。
小学生はまだ中学校で給食を食べますが、中学生は卒業後に給食を食べる機会はまずないでしょうから、寂しくなりますね。
いずれにせよ、食育センターの方々や調理員さんたちが「おめでとう!🎉」の気持ちを込めて精一杯のおもてなしをしてくださいます。今回のスペシャルメニューはもちろんのこと、これまでの給食すべてに感謝の気持ちでいただきましょう!

思わずそこらじゅうで「うわ~💛」「いいにお~い😋」と声が出ています。飾りや小物も含めて、これはほんとすごい!




待ちきれない🤤けど、待って、



栄養教諭さんや調理師さんのお話をお聞きし、

いざ!






では、いただきましょう!













たくさん用意してくださったおかげで、おかわりもしっかりできます。


最後はデザートも出てきました。



廊下を見ると、今まで見たこともないような量のバットが。
こんなに準備してくださったんですね。ありがたいね。
卒業前のいい思い出の一つとなりましたね。

食べ終わって、感謝の気持ちをみんなでお伝えして、





「本当にありがとうございました。ごちそうさまでした!!」
1~5年生の子たちも、1~5年後が楽しみだね!